

映像制作における動物福祉の未来 〜倫理的な撮影と代替技術の革新〜
1. ガイドラインの策定と普及
はじめに
映像制作における動物の使用は、視覚的なリアリティを高める重要な要素となる一方で、動物福祉の観点から慎重な取り扱いが求められます。適切な管理がなされない場合、動物が過度なストレスにさらされたり、不適切な環境で飼育・撮影されたりするリスクが生じます。
こうした問題を未然に防ぎ、映像制作業界における動物福祉の水準を向上させるため、日本動物福祉映像倫理委員会(GSA-JAPAN)は、動物の福祉を考慮したガイドラインを策定し、その普及活動に取り組んでいます。
ガイドライン策定の背景
従来、映画やドラマなどの映像作品では、演技をする動物が必要とされるシーンが多く、適切な訓練を受けた動物が起用されてきました。しかし、動物に対する倫理的な意識が高まるにつれ、以下のような問題点が指摘されるようになりました。
過度な負荷を伴う演技の強要
一部の撮影現場では、動物に本来の生態とかけ離れた動作をさせたり、ストレスを与える演技を強要したりするケースが見られました。安全管理の不備
撮影中の事故や負傷のリスクが十分に考慮されていないことがあり、動物が意図せず危険な状況にさらされる場合がありました。倫理的な問題
動物を単なる”撮影道具”として扱い、その健康や安全を十分に考慮せず使用する例が報告されていました。
こうした問題を解決するため、GSA-JAPANは動物福祉の専門家、映像業界の関係者、動物プロダクションなどと協力し、撮影現場での動物の適切な扱いに関する明確な指針を示すガイドラインを策定しました。
ガイドラインの基本原則
GSA-JAPANが策定するガイドラインは、以下の基本原則に基づいています。
動物の安全と健康を最優先
動物にストレスや危険が及ばないよう、撮影環境や演出内容を配慮する。本来の行動や生態に配慮
動物に不自然な行動を強要せず、可能な限り自然な状態での撮影を行う。専門家の監督のもとで撮影を行う
動物プロダクションや獣医師などの専門家の監修を受け、適切な指導と管理のもとで撮影を進める。過度なトレーニングや虐待を禁止
動物に苦痛を与える方法での訓練や、暴力的な扱いを一切禁止する。代替手段の活用を推奨
動物を使わずに表現できる場合は、CGやVFXなどの技術を活用することで、実際の動物への負担を減らす。
ガイドラインの適用範囲
GSA-JAPANのガイドラインは、以下のような映像制作の現場で適用されます。
映画・ドラマの制作現場
俳優と共演する動物の演技指導や安全管理を徹底。テレビCM・広告
動物を登場させる際の表現方法や撮影環境のチェック。ミュージックビデオ・プロモーション映像
動物を使用する場合は、事前に安全性を確認し、適切な方法で撮影を行う。ドキュメンタリー番組
野生動物を扱う際は、自然環境への影響を考慮し、過剰な接触を避ける。
これらのガイドラインは、映像制作に関わるすべての関係者が守るべき基本的な指針として機能し、動物が適切に扱われることを保証します。
普及活動と業界への影響
GSA-JAPANは、策定したガイドラインを映像業界全体に浸透させるため、さまざまな普及活動を行っています。
業界向けのワークショップ・セミナーの開催
映像制作関係者向けに、動物福祉の基礎知識やガイドラインの適用方法について学べるセミナーを実施。オンライン資料の提供
ガイドラインの内容を分かりやすくまとめた資料や動画を公式ウェブサイトで公開し、誰でもアクセスできるようにする。動物プロダクションとの協力
ガイドラインに準拠した動物トレーナーやプロダクションと連携し、業界標準の確立を目指す。映像作品への認証制度の導入
ガイドラインを遵守した映像作品には、動物福祉基準を満たしていることを示す認証マークを付与する取り組みを推進。
このような活動により、GSA-JAPANは業界全体の意識改革を促し、動物がより安全かつ倫理的に扱われる環境の整備を進めています。
今後の課題と展望
ガイドラインの策定と普及は一定の成果を上げていますが、さらなる改善点も存在します。
映像制作の現場での徹底
制作現場ごとに異なる慣習があり、すべての関係者にガイドラインを周知徹底することが求められます。国際基準との整合性
海外の動物福祉基準とも整合性を持たせ、国際的に通用するルール作りを進める必要があります。CG・VFXの普及と技術革新
動物の代替表現技術をさらに発展させ、リアルな映像表現を維持しながら動物の使用を最小限にすることが重要です。
GSA-JAPANは、今後も動物福祉の向上と映像業界の発展を両立させるため、継続的な取り組みを行っていきます。
このように、ガイドラインの策定と普及は、映像制作における動物の倫理的な扱いを確立し、より良い制作環境を生み出す重要な役割を担っています。

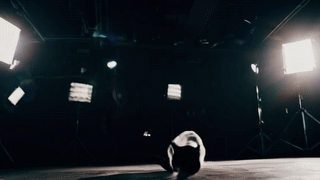
暗い撮影スタジオの一角。
まばゆいスポットライトが何度も点滅し、カメラのフラッシュが不規則に光る。
スタッフの大きな声が飛び交い、重い機材が床に置かれるたびに金属音が響く。
そんな喧騒の中、片隅にいる動物たちは不安げに身を縮め、怯えた表情を浮かべている。
まるで、小道具のひとつのように扱われる動物たち——。
これは、映像制作の裏側で繰り返される現実の象徴的なイメージシーンである。




2. 撮影現場での動物福祉の監修
はじめに
映像制作において、動物を使用するシーンは作品のリアリティを高め、視聴者に深い印象を与える重要な要素です。しかし、撮影環境が適切に整備されていなかったり、動物の行動に無理が生じる演出が求められたりすると、動物に大きなストレスや危険を与えてしまう可能性があります。
そこで、日本動物福祉映像倫理委員会(GSA-JAPAN)は、撮影現場での動物の福祉を確保するための監修活動を行っています。これは、動物が安全かつ健康的な環境で撮影に参加できるようにするための重要な取り組みです。
動物福祉の監修が求められる理由
動物が登場する映像作品の制作において、以下のような問題が発生する可能性があります。
動物の過度な負担
何度も同じ演技を繰り返すことで疲労が蓄積し、ストレスや健康被害を引き起こすことがあります。適切な休憩時間の確保不足
動物には人間と同様に休憩が必要ですが、撮影スケジュールが厳しいと、十分な休息が取れないまま撮影が進行してしまうことがあります。危険なシーンでのリスク管理不足
火や水を使う演出、高所での演技、急激な動きが求められるシーンなどでは、動物の安全確保が極めて重要になります。適切な食事・給水の提供がされない
撮影中の動物の食事や水分補給のタイミングを見落とすと、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの問題を未然に防ぐため、GSA-JAPANは撮影現場での監修活動を行い、動物の福祉を守る仕組みを確立しています。
撮影現場での監修活動の具体的な内容
GSA-JAPANの動物福祉監修は、撮影前・撮影中・撮影後の3つの段階に分かれて実施されます。
1. 撮影前の準備
撮影の前段階で、動物の福祉を考慮した計画を立てることが重要です。GSA-JAPANでは以下の点を確認します。
撮影内容のチェックとリスク評価
撮影台本を確認し、動物に過度な負担がかかる演出がないかを精査。リスクがある場合は代替案を提案します。動物のコンディション確認
使用する動物の健康状態や性格を事前に把握し、適した撮影方法を検討します。トレーナーや獣医の配置
動物プロダクションと協力し、撮影現場には必ず専門のトレーナーや獣医を配置するよう指導します。撮影環境の整備
照明や音響が動物に与える影響を考慮し、過度なストレスがかからない環境を整えます。
2. 撮影中の監督・管理
撮影中には、動物が安全で快適に過ごせるよう、GSA-JAPANの監修のもとで以下のポイントを徹底します。
動物の安全確保
動物が負傷しないよう、撮影セットや小道具の安全性を確認し、必要があれば修正します。動物の行動を自然に演出
無理な演技を強要せず、可能な範囲で動物の自然な動きを活かした演出を行います。適切な休憩と給水の確保
撮影の合間に適切な休憩時間を確保し、定期的に給水と食事の時間を設けるよう指導します。撮影スケジュールの調整
動物の体調や疲労度を考慮しながら、無理のない範囲で撮影を進行させます。トレーナー・獣医との連携
もし動物の体調に異常が見られた場合は、即座に獣医と相談し、必要な処置を講じます。
3. 撮影後のフォローアップ
撮影が終わった後も、動物の健康と福祉を確保するためのフォローアップを行います。
動物の健康チェック
撮影後に動物の体調を確認し、異常がないかを評価します。ストレス軽減のためのケア
動物が長時間の撮影でストレスを感じた場合、リラックスできる環境を提供し、必要に応じてケアを行います。撮影現場の評価と改善提案
撮影中の問題点を振り返り、今後の撮影でより動物福祉に配慮した環境を整備できるよう、制作側へフィードバックを行います。
監修活動による効果と業界への影響
GSA-JAPANが行う撮影現場での監修活動により、以下のような効果が期待できます。
動物が安心して撮影に参加できる環境が整う
撮影現場の動物福祉基準が向上し、動物が安全かつ快適に過ごせるようになります。業界の意識改革が進む
制作側の動物福祉に対する意識が高まり、より倫理的な映像制作の文化が根付くきっかけとなります。トラブルや事故の防止
事前の監修によってリスクを未然に防ぐことができ、撮影中の事故や動物の健康被害を大幅に減らすことができます。
今後の課題と展望
GSA-JAPANは、撮影現場での動物福祉監修をさらに強化し、より多くの映像制作現場に普及させることを目指しています。しかし、以下のような課題も残されています。
すべての制作現場での監修体制の確立
小規模な撮影現場やインディーズ映画などでは、動物福祉に関する専門家が関与しないケースもあるため、監修体制をより広範囲に適用する必要があります。動物に優しい演出のさらなる普及
映像制作において、そもそも動物に負担をかけない演出方法を取り入れる文化を広めていくことが重要です。
GSA-JAPANは今後も、動物福祉に配慮した映像制作を促進し、より安全で倫理的な撮影環境を実現するための活動を続けていきます。

3. 動物プロダクションとの連携
はじめに
映像制作において、動物の出演は作品のリアリティを高めるだけでなく、視聴者に強い印象を与える重要な要素です。しかし、動物を適切に扱わなければ、撮影中の事故やストレス、健康被害などの問題が発生するリスクがあります。そのため、専門的な知識と経験を持つ動物プロダクションと協力し、安全かつ倫理的な撮影環境を整えることが不可欠です。
日本動物福祉映像倫理委員会(GSA-JAPAN)は、動物プロダクションと連携し、動物の福祉と安全を確保しながら、映像作品の質を向上させる活動を推進しています。
動物プロダクションとは?
動物プロダクションは、映画、ドラマ、CM、ミュージックビデオなどの映像制作において、動物のキャスティングやトレーニングを担当する専門機関です。主に以下のような役割を果たします。
動物の選定とキャスティング
作品の内容に適した動物を提供し、演技が可能な個体を選定する。トレーニングと演技指導
動物が撮影に適応できるよう、事前に訓練を行い、指定された動作を無理なく再現できるよう指導する。健康管理と福祉の確保
動物が健康的に撮影に臨めるよう、獣医師と連携しながら適切なケアを提供する。撮影現場でのサポート
撮影中の動物の状態を監視し、安全な環境を維持しながら撮影が進行できるようサポートする。
GSA-JAPANと動物プロダクションの連携の重要性
GSA-JAPANは、動物プロダクションとの密接な連携を図ることで、映像制作現場での動物の福祉を向上させる取り組みを行っています。その目的は、以下の3点に集約されます。
動物福祉の基準を統一し、業界全体での意識向上を促す
動物プロダクションによって動物の扱い方には差があり、適切な基準が確立されていない場合もあります。GSA-JAPANは、動物福祉の基準を業界全体に広め、統一したガイドラインに基づいて運営されるよう促しています。適切な動物の管理体制を構築し、安全な撮影環境を提供する
事前の準備や撮影中の監督体制を整備することで、動物が不適切な状況に置かれることを防ぎ、安全で健康的な環境の中で撮影に参加できるようにします。動物を扱う専門家と制作側の橋渡しを行い、スムーズなコミュニケーションを実現する
映像制作の現場では、動物の扱いに詳しくないスタッフが多いため、動物プロダクションと制作側の間にGSA-JAPANが介在し、動物福祉を考慮した撮影を実現できるようにサポートします。
連携による具体的な取り組み
GSA-JAPANと動物プロダクションの連携により、以下のような具体的な取り組みが進められています。
1. 撮影前の準備段階での調整
- 動物プロダクションと制作側の打ち合わせを行い、動物の演技内容や撮影スケジュールを決定。
- 動物のコンディションを確認し、撮影前のトレーニング計画を作成。
- リスクのあるシーンでは、CGやVFXの使用を検討し、動物の負担を軽減。
2. 撮影中の安全管理
- 動物プロダクションのトレーナーが常駐し、撮影現場での動物の状態を監視。
- 長時間の撮影を避け、適切な休憩と給水の時間を確保。
- 万が一の事故に備え、獣医師を待機させ、緊急時の対応を迅速に行う。
3. 撮影後のフォローアップ
- 動物の健康状態を確認し、ストレスがかかっていないかをチェック。
- 撮影の振り返りを行い、問題点を洗い出して次回の改善点を整理。
- 制作側へフィードバックを提供し、動物福祉に配慮した撮影方法の改善を促す。
動物プロダクションとの連携がもたらす効果
GSA-JAPANと動物プロダクションの連携により、以下のような効果が期待できます。
動物が適切な環境で撮影に参加できる
専門のプロダクションが関与することで、動物にとって快適で安全な環境が提供される。映像業界全体の動物福祉基準が向上する
動物プロダクションと制作側の協力により、業界のスタンダードが確立され、倫理的な撮影が一般的になる。視聴者の信頼が高まる
動物の福祉に配慮した作品は、視聴者からの評価が向上し、倫理的な映像制作を支持する流れが強まる。
今後の課題と展望
動物プロダクションとの連携は、動物福祉の向上に大きく貢献しますが、さらなる課題もあります。
小規模な制作現場への導入
低予算の作品では、動物プロダクションを利用するコストがかけられない場合もあるため、支援策を検討する必要があります。新しい技術との融合
CGやVFX技術の進化により、実際の動物を使わずにリアルな映像を作る方法が増えているため、動物プロダクションと技術者が協力し、負担の少ない撮影手法を確立することが求められます。
今後もGSA-JAPANは、動物プロダクションとの連携を深め、動物の福祉を守りながら映像業界の発展に貢献していきます。

4. 教育・啓発活動
はじめに
動物が関わる映像制作において、その倫理的な扱いと福祉を確保するためには、業界関係者だけでなく一般の人々の意識向上も不可欠です。日本動物福祉映像倫理委員会(GSA-JAPAN)は、動物の適切な取り扱いについての知識を広め、映像業界全体に動物福祉の重要性を浸透させるために、さまざまな教育・啓発活動を展開しています。
この活動を通じて、撮影現場での動物虐待を防ぎ、倫理的な映像制作文化を確立することを目指しています。
教育・啓発活動の目的
GSA-JAPANの教育・啓発活動は、主に以下の3つの目的に基づいています。
映像業界関係者への意識改革
監督、プロデューサー、撮影スタッフ、俳優など、映像制作に関わるすべての人々に動物福祉の知識を提供し、現場で適切な行動をとれるようにする。一般の人々への正しい情報の発信
視聴者に対し、映像作品における動物の扱い方の現状を伝え、倫理的な作品選びや動物福祉に関心を持つきっかけを提供する。新しい技術や代替手法の普及
CGやVFXを活用した動物表現の可能性を紹介し、実際の動物の負担を減らす方法を業界内に広める。
教育・啓発活動の具体的な取り組み
GSA-JAPANは、上記の目的を達成するために、以下のような教育・啓発活動を積極的に実施しています。
1. 業界向けワークショップとセミナーの開催
映像業界の関係者を対象に、動物福祉に関するワークショップやセミナーを定期的に開催しています。これにより、動物の適切な扱い方や撮影時の注意点について実践的な知識を提供します。
セミナーの内容
- 動物のストレスを軽減する撮影手法
- 動物プロダクションとの適切な連携方法
- 海外の動物福祉基準と日本の映像業界への適用
- 事故を防ぐための安全管理方法
ワークショップの特徴
- 実際の撮影現場を想定したシミュレーション
- 動物トレーナーや獣医師による指導
- 撮影現場での具体的な問題解決策の提案
これらの教育機会を通じて、制作現場での動物の福祉意識を高め、より倫理的な映像制作を促進します。
2. 一般向けの啓発キャンペーン
映像作品を視聴する一般の人々に対しても、動物福祉に関する正しい知識を伝えるためのキャンペーンを実施しています。
SNSやWebサイトでの情報発信
- 映像業界における動物の扱いに関する最新ニュースの発信
- 動物福祉に配慮した映画・ドラマの紹介
- 視聴者が知っておくべき動物の権利に関する情報提供
オンラインイベントの開催
- 映像作品に登場する動物の裏側を知るトークイベント
- 動物福祉を考慮した映像制作の可能性を探るディスカッション
- 動物トレーナーや映像監督との対談
学校や動物愛護団体との連携
- 若い世代に向けた教育プログラムの提供
- 学校教材として使用できる映像資料の作成
- 動物愛護団体と協力した共同プロジェクトの実施
これらの活動により、一般の人々の間でも動物福祉への理解が深まり、倫理的な映像作品への支持が広がります。
3. 代替技術(CG・VFX)の推進
動物の負担を軽減するために、GSA-JAPANはCGやVFXを活用した映像制作の推進にも力を入れています。
VFX技術の紹介
- 近年のCG技術の進歩により、実際の動物を使用せずにリアルな映像を作ることが可能になっています。
- 海外の事例を交えながら、VFXを活用した動物表現の成功事例を紹介。
制作現場への導入支援
- 監督やプロデューサー向けに、CGを活用した映像制作のガイドラインを提供。
- CG制作会社と映像制作チームをつなぎ、実際の撮影で動物を使用する代替手段として活用できる環境を整備。
成功事例の共有
- CGを活用した動物表現がどのように作品のクオリティを向上させるかを示す事例を業界内に広める。
- 実際に動物を使わずに制作された映画やドラマの紹介を行い、制作側の関心を高める。
これらの取り組みにより、動物を実際に使用しなくても高品質な映像作品を作る方法が広まり、映像制作における動物の負担を大幅に軽減することが可能となります。
教育・啓発活動の効果
GSA-JAPANの教育・啓発活動により、以下のような効果が期待できます。
映像業界の意識向上
業界関係者が動物福祉の知識を持つことで、撮影現場での動物の扱いが適切になり、虐待やストレスを伴う撮影が減少する。視聴者の意識変革
一般の人々が動物福祉に関心を持つことで、倫理的な映像作品を求める声が高まり、業界全体が倫理的な制作方法へとシフトしていく。動物を使わない映像制作の普及
CGやVFX技術の発展とともに、動物を使用しない映像制作が増え、動物への負担が軽減される。
今後の課題と展望
GSA-JAPANの教育・啓発活動は一定の成果を上げていますが、さらなる発展のためには以下の課題に取り組む必要があります。
教育プログラムの充実
業界関係者向けの教育機会を増やし、動物福祉に関する知識を広める。国際的な動向の取り入れ
海外の動物福祉基準と日本の映像業界の実情を比較し、より効果的な施策を導入。視聴者への情報提供の強化
映像作品における動物の扱いに関する情報を、視聴者が簡単に入手できる仕組みを構築する。
今後もGSA-JAPANは、教育・啓発活動を通じて、映像業界と社会全体の動物福祉意識を高め、持続可能な映像制作環境の実現を目指します。

5. 動物の代替技術の推進
はじめに
映像制作において、動物の存在は作品のリアリティや感情表現を高める重要な要素となります。しかし、撮影のために実際の動物を使用すると、ストレスや負担がかかるだけでなく、虐待や事故のリスクも伴います。さらに、野生動物を扱う場合は、自然環境への影響や倫理的な問題が発生する可能性もあります。
こうした課題を解決するために、日本動物福祉映像倫理委員会(GSA-JAPAN)は、CG(コンピューターグラフィックス)やVFX(ビジュアルエフェクト)などの動物の代替技術の推進に力を入れています。これにより、動物を使用せずにリアルな映像を作ることが可能となり、動物福祉と映像表現の両立を実現します。
動物代替技術の必要性
従来の映像制作では、動物を直接撮影することが一般的でした。しかし、以下のような理由から、CGやVFXを活用した代替手法の導入が求められています。
動物の負担軽減
撮影のために訓練を受けたり、長時間待機したりすることは、動物にとって大きなストレスとなります。特に、炎や爆発、急な動きが伴うシーンでは、動物の安全を確保することが困難です。CGやVFXを活用することで、実際の動物を使わずにリアルな映像を作成でき、動物の負担を大幅に軽減できます。倫理的な問題の解決
一部の映像作品では、動物の扱いが不適切であると批判されることがあります。たとえば、過去には映画撮影中に動物が怪我をしたり、不適切な飼育環境で扱われたりするケースが報告されていました。動物代替技術を活用することで、こうした倫理的な問題を回避できます。撮影制約の克服
実際の動物を使用すると、思い通りの演技を引き出すことが難しく、撮影スケジュールにも制約が生じます。一方で、CGやVFXを活用すれば、動物の動きや表情を自由にデザインでき、より精密な映像表現が可能となります。希少種や野生動物の保護
絶滅危惧種や野生動物を撮影する際には、自然環境への影響や捕獲のリスクが伴います。動物代替技術を活用すれば、動物の生息地を破壊することなく、リアルな映像を制作できます。
GSA-JAPANの取り組み
GSA-JAPANは、動物代替技術の推進のために、以下のような具体的な取り組みを行っています。
1. 最新技術の調査・研究
CGやVFXを活用した動物表現の技術は年々進化しており、よりリアルな映像が制作可能になっています。GSA-JAPANは、以下のような最新技術の調査・研究を行い、映像業界に普及させる活動を進めています。
モーションキャプチャ技術の活用
俳優や動物の動きをセンサーで記録し、リアルなアニメーションを生成する技術。たとえば、ハリウッド映画では、動物キャラクターの演技を人間の俳優が演じ、モーションキャプチャで動きをCGに変換する手法が一般的になっています。AIを活用したリアルタイムCG
AI技術を活用し、実際の動物の動きや表情を学習してリアルタイムでCGに変換する技術。これにより、撮影現場でのリアルな動物表現が可能となります。フォトリアルなVFX技術
実写と区別がつかないほどリアルなCGを作成するためのレンダリング技術。特に、毛並みや瞳の表現技術が進化し、本物と見分けがつかないレベルの映像が制作可能になっています。
2. 映像業界への技術導入支援
最新の動物代替技術を映像業界に導入するため、GSA-JAPANは以下のような支援を行っています。
制作チームへの技術紹介
映像制作者向けに、最新のCG・VFX技術の活用事例や導入方法を紹介するセミナーを開催。代替技術を活用した映像作品の普及
実際にCGやVFXを活用した作品を紹介し、成功事例を業界内に広めることで、動物を使わない映像制作の意識を高める。技術者とのマッチング支援
映像制作チームとCG・VFXの専門家をつなぎ、動物代替技術を活用しやすい環境を整備。
3. 動物プロダクションとの連携
GSA-JAPANは、動物プロダクションと協力し、CGやVFXの導入を進めています。たとえば、実際の動物をスキャンしてデジタルモデルを作成し、そのデータを活用することで、リアルな動物の動きをCGで再現する取り組みを進めています。
また、動物トレーナーの知識を活かし、CGの動物が自然な動きをするようにアニメーションの調整を行うプロジェクトも推進しています。
動物代替技術の普及による効果
動物代替技術が普及することで、以下のようなメリットが生まれます。
動物の負担をゼロにできる
実際の動物を撮影現場に連れて行く必要がなくなり、ストレスや健康被害のリスクが完全になくなる。撮影の自由度が向上する
どんな動物でも、どんな動作でも、CGなら自由に表現可能になり、よりクリエイティブな映像制作ができる。制作コストの削減
一見するとCGの方がコストが高く思えるが、長期的には撮影の制約が少なくなるため、全体の制作費を削減できる。
今後の課題と展望
GSA-JAPANは、動物代替技術のさらなる普及に向けて、以下の課題に取り組んでいきます。
技術開発の加速
よりリアルな動物表現を実現するため、最新技術の研究を進める。制作現場での活用推進
まだCG技術に馴染みのない制作チームにも、導入しやすい環境を整える。視聴者の理解を深める
CG動物を使った作品の価値を視聴者に伝え、倫理的な映像制作を支持する文化を醸成。
GSA-JAPANは、今後も動物の負担を最小限に抑えつつ、映像業界の発展に貢献する技術革新を推進していきます。


保護犬 保護猫
救済支援ステッカー
Pink

保護犬 保護猫
救済支援ステッカー
Green

保護犬 保護猫
救済支援ステッカー
Yellow

緊急災害時 動物救済
活動支援ステッカー
Red

緊急災害時 動物救済
活動支援ステッカー
Blue

野良猫 救済
TNR活動
推進支援ステッカー

野生動物 傷病鳥獣
保護支援ステッカー

TANUKI
タヌキ精鋭部隊
ミリタリーステッカー

TANUKI
タヌキ精鋭部隊
ミリタリーワッペン
当サイトは、Amazonアソシエイト・プログラムに参加しており、Amazon.co.jpの商品を紹介し、リンクを通じて紹介料を得る仕組みを採用しています。皆さまに価値ある情報をお届けしながら、サイト運営を支えるためのプログラムです。


